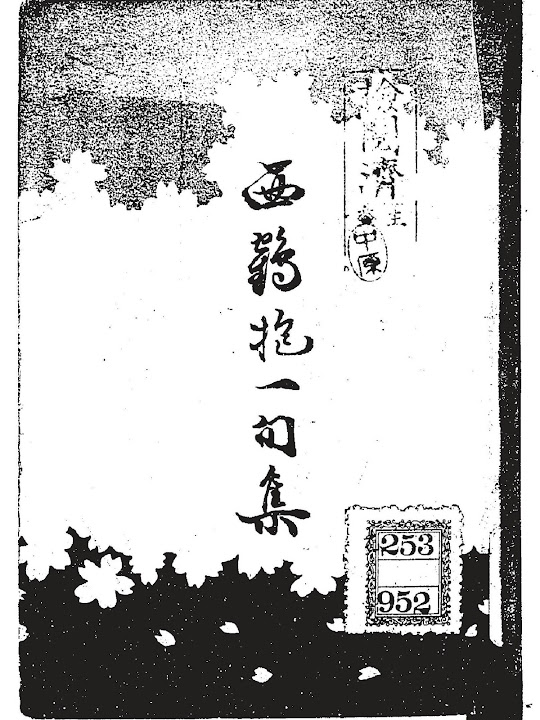短歌同人誌『率』の2号を読んだ。『率』は、力のある若い歌人が集う同人誌で、ぺらぺらの薄い冊子であるが、読み応えは十分であった。特に、小原奈実の連作「
まず、小原奈実の「
黙すことながきゆふさり息とめて李の淡き谷に歯を立つ
肉体のわれを欲るきみ切りわけし桃に褐変の時が過ぎゆく
この2首が印象に残った。2首とも二句切れのいわゆる万葉調(五七調)で、第二句までが心情的な描写、第三句からが実景的な描写という構成になっている。心情的な部分と実景的な部分を分ける手法は現代短歌に於て「王道」とでも呼ぶべき、ある種定番ともなっているもので、作者の世代や志向を越えて広く用いられている。それにも関わらず、私はこの2首にある種の「驚き」と「新しさ」を感じずにはいられない。
心情的な描写からするすると作品世界に入ってゆくわけだが、それぞれ第三句あたりまで差しかかったところで驚くべき表現に出くわすことになる――「息とめて李の淡き谷に歯を立つ」、「切りわけし桃に褐変の時が過ぎゆく」――突如立体的に浮上する「李」と「桃」の存在感にはっと息を呑む思いがする。
これらの表現に傑出している部分をより詳細に考察してみたい。まず一首目では、「淡き谷」という「李」の一側面を端的に切り取り、そこに局所的に「歯を立」てる。二首目では、桃が「褐変」してゆく様を「時が過ぎゆく」という大きな時間の幅で捉えてゆく。「李」と「桃」という存在の「淡き谷」、「褐変」という視覚的、外観的にユニークな特徴が示され、そこに外観以外の動きが加えられることで、対象が言葉の上に立体的に立ち上がって来るというわけだ。このような描写は、作者の「李」や「桃」のような小さな「もの」――あるいは「生命」――に対する確かな関心と、それに基づく観察の成果を表しているように思う。そして小原奈実の「新しさ」というのは――この立体的な情景描写自体が既に革新的であることに加えて――このような表現が、いわゆる「客観写生」のような無味乾燥な文脈に置かれるのではなく、情感豊かな文脈の中に、
平岡直子の「装飾品」には、
ピアニストの腕クロスする 天国のことを見てきたように話して
完璧な猫に会うのが怖いのも牛乳を買いに行けば治るよ
これだから秋は、ときみは口ずさみ怪獣みたいな夕焼けだった
こんな歌があった。「ピアニストの腕クロスする」、「完璧な猫」、「怪獣みたいな夕焼け」――恐るべき強度を持ったフレーズが突き刺さるように響く。そしてそこに「牛乳を買いに行けば治るよ」とか、「これだから秋は」というように、語りかけるような優しさで、不可解な内容が示唆される。ほとんどわからないぎりぎりのところで、わかる、といった印象であろうか。言葉の強度は感性の壁を越えるのかもしれない。